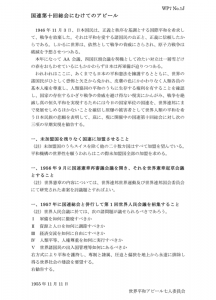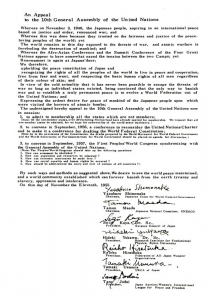アピール WP7 No.99J
2009年11月6日
世界平和アピール七人委員会
武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 井上ひさし 池田香代子 小沼通二 池内了
2010年10月に名古屋で開かれる生物多様性条約第10回締約国会議を一年後に控えて、世界平和アピール七人委員会は、日本を含む同条約の締約国のみならず全世界のすべての国々とその市民が、生命とその多様性を尊重する責任の重大さについてさらなる理解を深めることを希望し、米国に対しては同条約の速やかな批准を求めて、以下のとおり呼びかける注。
(1) 人類の地質圏・生命圏に及ぼす破壊力の自覚の必要性:
人間は、生物の進化の到達点として、地質圏・生命圏の上に知識圏を形成し、科学技術を駆使して自然を改変してきた。核エネルギーから遺伝情報までを自由にあやつる力を手にした現代の社会は、人類にとって有益なサービスを自然から大きく引き出す能力を備えるに至った。しかもその能力は、悪用すれば、地球上に生息する生命の多様な種を絶滅させることができるレベルに達したのである。
1955年に核兵器と戦争の廃絶を訴えて、世界の科学者の運動の端緒を切り開いたラッセル・アインシュタイン宣言注は、生物の種の一員である人類の絶滅の現実的危機に対する警告であった。
生物多様性条約第10回締約国会議が開かれるに際して、われわれは、人類が、いまや生命圏と地質圏を破壊する能力をもつにいたったことを、改めて自覚する必要がある。
(2) すべての生命体の「平和に生存する権利」に基づく倫理的・規範的基準を確立する必要性:
今日、幸いにして核兵器に関しては、その廃絶を求める国際世論が高まっている。しかし、多様な種を絶滅に追い込みかねない人類による脅威は、グローバル化する新自由主義経済の圧力のもとで依然増大の一途をたどっている。いまわれわれは、「地球憲章」注(2000年)にのっとり、かつ日本国憲法前文にある「平和に生存する権利」をすべての生命とともに人類が共有すべき大原則として再確認し、人類のすべての活動を律する倫理的・規範的な基準を確立すべき時に至っている。
(3) 知識開発・権力行使・市場活動の規制の必要性:
いま求められているのは、グローバル・ガバナンスにおいて決定権を握っている者たち、すなわち知識開発を担う科学技術専門家や技術官僚、政治権力保持者、市場や金融を動かす企業家たちの倫理的自己規制であり、それを不可避にする国内・国際を通じての法規制である。地球憲章は問題提起として重要であり、生物多様性条約は必要な要件を法的に表現しているが、それだけでは十分でない。たとえば、遺伝子組み換えなど、悪用されれば生命圏破壊の原因となる可能性のあるバイオテクノロジーの研究開発は、人類の良識ある倫理意識によって自己抑制されるとともに、予防原則に則った法的規制の可能性が検討されるべきである。
(4) 生命の多様性を持続可能にする新しい循環型の市場経済を構築する必要性:
人類は、産業革命がおこるまでの数千年間、農耕によって多様な生命体間のサービスの循環的な相互補完・共同利用を再生産することで、生態系資源からのサービスを受けつつ、「里山」などの二次的自然を造るなど、生命圏へ「お返し」をする循環型の生命系維持的経済を営んできた。
しかし、欧米中心に築かれた資本主義市場経済は、生態系からのサービスを可能な限り活用して、今日のグローバル金融資本主義にまで成長した。工業化と都市化によって生態系を徹底的に利用する文明は、大量生産・大量消費・大量廃棄を重ねるとともに、商品としての価値のみから多様な生命を選別してきた結果、資源のグローバルな商品価値に起因する貧富の格差が拡大し、生物種の生存そのものが脅かされるに至っている。
今日の世界的金融危機は、この市場経済の成長路線が持続不能なものであることを明らかにしているが、持続不能性はそれにとどまらず、生物資源の減少と温暖化などの生命圏・生態圏の異変に深刻に表れている。このような中で、人類の3分の2はいまだに生命系維持的経済のなかで経済成長を待つ状態に置かれている。生物多様性条約は、この不均等な遺伝資源をはじめとする生態系資源の公正な配分を目的の一つにかかげている。必要なことは、人間生活の豊かさを犠牲にして市場経済以前の生命系維持的経済に戻ることではなく、生態系サービスの商品としての配当を単に人間の間で再配分することでもない。むしろ、人々の暮らしと多様な生命体の暮らしとが相互に豊かになる方向に向かうべきである。つまり、生命の多様性を持続可能にする新しい循環型の市場経済を構築していくことが必要なのである。
生物多様性を保障するために使う指標は、生物種の減少を示すものだけでは十分ではない。グローバル市場金融経済による生態系全体の破壊傾向の規制と、この破壊傾向に抗したライフスタイルを採用する市民と地域経済の形成に関するものも含めなければならない。
(5) 伝統的な知識・工夫・慣習に学ぶ教育に基づく改革実践の必要性:
グローバル市場経済を生命系維持的経済のなかに埋め込んで、新しい多様な生命に開かれたものにするためには、生物多様性条約(第8条j項注)にあるように、生命系維持的経済を今日も維持している先住民族共同体や伝統的な「むら」共同体の知識・工夫・慣習に学び、人類と他の生命体との間のサービスの相互交換に根ざした持続可能で自立的な地域経済を形成すべきである。
そのためには、外からグローバル・スタンダードを押し付けるのでなく、ローカルな市民のライフスタイルの改革を基盤にして、国連が進めている「持続可能な開発教育」を一層重視して意識改革を図り、地域共同体の経済改革を着実に積み上げていく必要がある。
(6) 貧困の克服と地域経済の活性化に努める必要性:
先住民族の共同体や、伝統的な地域の共同体は、グローバル経済にさらされながら長年にわたり自然に身につけて来た知恵を依然として持ち続けている。アジアをはじめ、アフリカ・ラテンアメリカの農村・山村・漁村では、里山との共生などの生命系維持的経済の伝統を守り続けている。これらの経済は、自立的に再生させ、生命の多様性を損なっている均質化やグローバル化から解放しなければならない。
生命系維持的経済の再活性化を進めるにあたっては、生態系の資源がより公正に配分されなくてはならない。こうした原則は、先進工業諸国のみならず開発途上諸国においても尊重され、開発計画の中で重要な役割を果たせるよう考慮されなくてはならない。これらの地域では、住民参加により、生命系維持的経済を否定しない形での開発によって、貧困の克服と地域経済の活性化に努める必要がある。
私たち世界平和アピール七人委員会は、全ての生物種の「平和に生存する権利」に基づく倫理的・規範的基準を確立し、市場経済を生命系維持的経済に融合させる方向で、ポスト2010年に設定される行動計画・ロードマップの最終年にあたる2020年に向けて、多様な生命体の絶滅を食い止めるグローバルな経済改革を推進するよう世界各国の政府と市民に訴える。
注
生物多様性条約とその締約国会議
生物多様性条約(Convention on Biological Diversity)は1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)で採択された条約の一つであり、翌1993年に発効した。日本は1992年に署名し翌年加盟した。米国は1993年に署名したが加盟していない。
この条約は、生物の多様性を「生態系」、「種」、「遺伝子」の3つのレベルで捉え、生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正な配分を目的としている。
締約国会議は、この条約の実施状況を検討するために、2年ごとに定期的に開かれている。
ラッセル・アインシュタイン宣言
1954年の水爆実験による第五福竜丸などの被曝の意味を直視したバートランド・ラッセル、アルバート・アインシュタイン、湯川秀樹たち11人が、1955年に、人類という種の一員としての立場にたって、核兵器の発展が人類絶滅の危機をもたらしていることを説いて、核兵器と戦争の廃絶を世界、特に科学者、に訴えた宣言。1995年にノーベル平和賞を受賞した世界の科学者のパグウォッシュ会議は、この宣言を受けて誕生した。
地球憲章
1984年に国連に設置された「環境と開発に関する世界委員会」(ブルントラント委員会)の呼びかけによって、地球規模の環境問題の解決のためには、人々の考え方、行動を変えるような哲学、倫理観、行動規範が必要だとの考えに立って、持続可能かつ平和で公正な社会を築くための価値や原則を謳い、行動指針を提示した文書。2000年に完成、発表された。
生物多様性条約 第8条(j)
「自国の国内法令に従い、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統的な生活様式を有する原住民の社会及び地域社会の知識、工夫及び慣行を尊重し、保存し及び維持すること、そのような知識、工夫及び慣行を有する者の承認及び参加を得てそれらの一層広い適用を促進すること並びにそれらの利用がもたらす利益の衡平な配分を奨励すること。」(全文)
PDFアピール文→  99J.pdf
99J.pdf