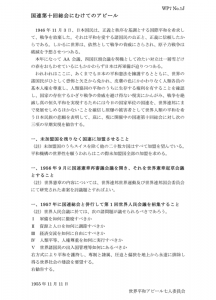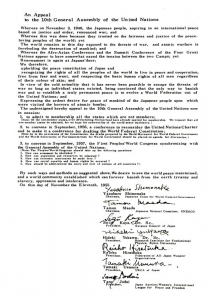電気を栽培
青々とした田畑、小高い山々とその先の阿武隈山脈、白くたなびく雲。福島の農村地はこうした光景が多い。海からの風を感じながら浜通りを横川ダムのある西の方へあがる。原発事故から7年が過ぎたこの夏の始め、酪農家の瀧澤昇司さんを訪ねた。
「牧草刈りに追われて」と日焼けした肌の汗をぬぐいながら満面の笑みを見せた。「私の畑では作物も作るけれど、電気も作っているんだ」。エッ?…畑で電気を作る?…口ごもりながら私は滝澤さんのキラキラした眼に吸い込まれるように次の言葉を待った。すると、彼は「だって、放射能は何百年、何千年と残るからそれと闘わなければならないと、あなたは言ったじゃない。あれで私は考え込んだんだ」と続けた。
それは2012年に福島県南相馬市の原町で行った七人委員会の講演会だった。放射能がいかに人類と共存できないかについて私も率直に語った。その時、彼は涙ぐんでいた。その涙が前向きに立ち上がらせた。「あれから真剣に電力を作ることに舵を切った」と彼は俄かに深い
思い返せば、瀧澤さんの牛舎を初めて訪ねたのは2011年、原発事故から1か月半が過ぎたころだった。痩せこけた30頭くらいの乳牛を前に「50頭くらいいたんだけれどね」と寂しそうに呟いた。牛乳の集荷は禁止されたものの、生きた牛の搾乳も餌も毎日どうしても欠かすことができない。絞っては畑に捨てる歳月が流れる。強い日差しのもと「オレは何やってんだと情けなくなるよ」と顔を手で覆った。
その後、集荷は許可されて彼の表情も和らいでいったが「このままでいいのか」という疑問は続く。そして「オレはセシウムと闘っているから何でも試すよ」と言っていたその時期に、七人委員会の講演会に行き会ったのだった。
「発電は電力会社を頼らないで得たい」と人生を賭けたように話して以来、牛舎の屋根から始まったソーラーパネルは訪れる度にぐんぐんと増えていった。今では営農型太陽光発電の設備は11か所、88アール、出力は550kwにまで拡大して収入を得られるようになった。畑には高さ3.5mの柱にソーラーパネルがずらりと並び、さらに拡張しつつある。雨や朝夕の効率が悪い分はパネルの枚数でカバーする。牧草を刈るためのトラクターも入る。
「放射能を帯びて使えなくなった田畑を放置するんじゃなくて、作物と一緒に電気も生産すれば、作物だけよりは儲かる。柱が短いパネルの下だと、日陰を好むネギとか榊がいいね。これは福島だけでなく、田舎の若い人たちの将来にも通じると思うよ」。
福島の人たちには東北電力の電気が供給されている。瀧澤さんにとっての原点は、使ってもいない東京電力福島第一原発の甚大な事故に対する怒りにある。原発立地から離れているにもかかわらず放射能に汚染された田畑を消極的に受け入れるのではなく、そこから汚染と無関係な電気を生み出すという発想と積極性はすばらしい。息子たち次世代のためにも、瀧澤さんは畑で「電気を栽培」すると決めて努力を重ねる。有言実行だ。広がる緑の大地、刈り取った牧草の白いロール、そしてソーラーパネル。その光景を私は頼もしくも眩しくも感じながらしばし緑の大地に佇んでいた。