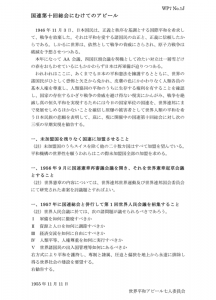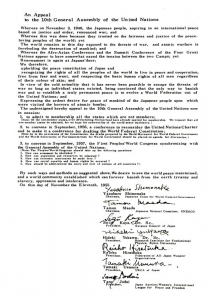一市民の意思と理性が問われている
先日、デジタルデータの消失問題を取り上げた朝日新聞の記事を読んだ。人類はいま、ほぼ数十年でデータの読み出しができなくなる記録媒体の物理的劣化や、読み取り装置を動かす基本ソフト(OS)が失われる可能性など、きわめて深刻な事態に直面しているという内容だった。このまま手を打たないでいると、民族の歴史、国家、政治、文化、技術、日々の暮らしのあれこれなど、私たちの文明の姿を伝える情報の多くが百年後、千年後には消えてしまい、未来の人びとは西暦二千年前後の地球の姿がどんなふうだったのかを知ることができない「空白期間」が生まれる、というのである。
昔、『タイムマシン』というアメリカのB級映画を観た。タイムマシンを発明した科学者が機械の故障で80万年後へ飛んでしまう荒唐無稽な話だったが、いまでも一つだけ忘れられないシーンがある。時間旅行の途中で立ち寄った2030年のニューヨークの図書館に、人類の知識を全部詰め込んだAIのホログラムが登場する。そして、人類の文明が滅びて原野に還ってしまった80万年後の地球にタイムマシンが着いたとき、荒れ果てた草原のなかにあのホログラムの装置だけが残っていて、誰もいない原野で延々と図書館の案内をしているのである。言い換えれば、映画が制作された2002年当時の映画人たちは、「デジタルデータだけが残って、それを利用する人間がいない」という状況を想像することはできたが、今日問題となっているようなデジタルデータそのものの消失と、それがもたらす歴史の空白は想定外だったということだろう。
一方で、くだんの記事を読みながら、高野山大学の書庫に眠る厖大な古文書や、世界記憶遺産に登録された東寺百合文書を思い出した。それらは、たまたま紙の劣化を最小限に留める気象条件や保管状況が揃っていただけではない。仏教寺院の本山から末寺に至るまで、あるいは朝廷から地方の役所まで、どんな些細な文言もおろそかにしない記録第一、継続性第一の不文律が、そうした文書の保存につながったと言われている。また、この国では為政者から商人まで、どんな文書も手文庫に収めて大切に保存し、不要になったものは襖の下貼りに使ったりして、けっして安易に捨てることはなかった。ときどき古民家で発見される襖の下貼りなどの古文書が、どれも一級の歴史史料や民族資料になる、こんな国は世界じゅうどこを探してもないらしい。
もちろん、そんなわが国でも、ときの為政者が記した「○○記」「△△録」などは、貴重な歴史史料ではあっても、必ずしもすべてが史実とは限らないし、人びとはつねに都合の悪い事実を書き換えたり、破棄したりしてきた。現代に至っても、先の戦争では、敗戦時に政治家と官僚と軍隊が公文書をあらいざらい廃棄したおかげで、私たちの戦後は歴史の検証も確定も出来ない未曾有の不幸とともに始まったのだが、それでも今日、公文書の管理と保存の徹底を求める国民の声は必ずしも大きくない。
古今東西、都合の悪いことは隠すのが人間の本態である。官僚はいつの世も、組織と権益の死守が本態である。だとすれば、欧米に根付いている公文書管理の仕組みなどは、共同体の強力な意思と合意と強制力があって初めて可能になるものなのだと言えよう。ひるがえってわが国では、東寺百合文書のように文書を大切に保管する習慣と、国民の財産としての公文書管理という民主主義社会の制度がうまく接続できない状況が続いている。
くだんのデジタルデータの問題も、その長期保存の必要性を認識しているのは、人間の都合や当面の政治状況ではなく、歴史の空白をつくってはならないという普遍的な意思と理性である。私たちに決定的に欠けているのは、これにほかならない。