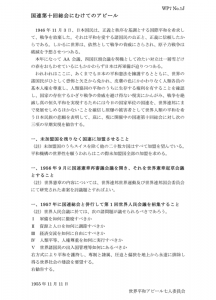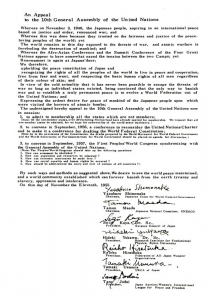新型コロナウィルスと戦争
新型コロナウウィルスに世界中が侵されている。連日、このニュースが押し寄せてくるから否応なく緊張する。この状態は大勢の死者を出したスペイン風邪の時と似ていると言われるものの、百年も前だから実感はない。大勢が集まる所は避けるようにと言われるが、真夜中以外の都会は何処へ行っても人は多い。花粉症や単なる軽い風邪などでも咳やくしゃみ、鼻水は容赦ない。側に居る人が見返す眼には敵意が色濃く漂っているなど、脅威の気持ちを露にする様子が通勤電車や店内でもよく目にする。
まるでこれは戦争だ。特に内戦といった誰が敵か分からない状況に似ている。どこで見張られているのか分からない。敵は物陰から銃をこちらに向けてタイミングを狙っているのだろうが、その姿は見えない。こうした状況は戦時下ばかりか権力闘争下の現代社会にも繋がっている。権力者ばかりか平凡な市民も対象になり兼ねないから、不用意な言動で身に危険が及ばないとも限らない。
これは妄想かもしれないが、戦禍を取材して40年間ほどの私の経験が俄かに湧き上がって、世界大戦を潜り抜けた人たちへと思いは馳せる。新型コロナウウィルスが蔓延し始めた冬から春の季節、75年前の欧州では戦火が止んで砲弾や虐殺から解放された。けれど、人びとの内側では戦争は終わらなかった。アジアの人びとにも進軍した日本兵にも、そして沖縄の人びとにもそこで闘った日本兵にも、みな夫々の内なる傷が残った。原爆を投下された広島、長崎の被爆者もその家族も戦争がいまだに終わらない闇を抱えている。
さらに、日本と同盟国のドイツがポーランドに侵攻してユダヤ人をゲットーに隔離し強制収容所で何百万人も惨殺した負の遺産にも、このウィルスの事態は重なってくる。強制収容所などから生還した人たちを取材して私が痛感したことは、誰もが今なお深い悩みの淵にいることだった。そうしたポーランド人にとってドイツは敵以外の何者でもない。けれど思い出すのは、中には人間性を重んじて「できるだけ助けたい」と何十人ものユダヤ人やポーランド人を助けたドイツ軍将校もいたことだ。彼はソ連軍の捕虜となって助けた事実を訴えたが無視され、ソ連の収容所で7年後に亡くなった。これはW・シュピルマン著「戦場のピアニスト」に登場するドイツ人国防軍将校のW・ホーゼンフェルトの実話である。
ソ連当局にはポーランド人は下等な人間だから助けるには値しないという根強い考えがあったようだ。そう言えば、カチンの森事件のようにポーランド人にとっての敵はドイツばかりではなく、救援者だと思っていたソ連もまた厳しい存在になった。
話はそれたが、新型コロナウィルスがどのような状態で私たちを襲ってくるかわからないと言うことだ。昨今の社会は一見平和そうだが、とんでもない複雑な事態を抱え込み、状況はまさにあの戦禍の時代を彷彿とさせる。それだけに私たちは見えない相手を見つけ出して、何とか殲滅しなければならない。
こうした切迫感に組み込まれつつある隙に、為政者が指導力の真髄を忘れて自分らの延命を図る策に邁進したらどうなるか。油断はできない。味方だと思っていたら敵になっている、その逆もまたあることを負の遺産に学びながら私たちは新型コロナウィルスと戦う。そのうちに、ワクチンと対処法が見つかり感染者の増加が世界中で止まる日は必ずくる。それまで細心の注意を怠らずに対処していくしかないだろう。