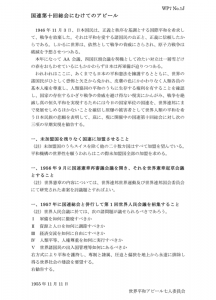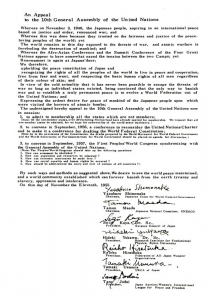チェルノブイリへの思い
旧ソ連のウクライナ北部にあったチェルノブイリ原発事故から30年になる。原発は1986年4月26日午前1時24分に4号炉で人為的なミスによって大爆発を起こし、レベル7の値に達した。高濃度の放射性物質が気流に乗ってベラルーシ、ロシアばかりかヨーロッパにまで拡散し世界中に及んだ。日本でも「雨に濡れたくない」という話題が巷に流れたりした。
ソ連から発信される情報は制限されていたが、医師や科学者、ジャーナリストたちによって徐々に知れ渡り始めた。人びとがどのような状態にあるのかをさらに取材しようと1990年、私も現地を訪れた。現場である地元は想像以上の過酷さに見舞われていた。
4年も経っていたものの、広大な被災地は避難したあの日のまま、いえそれ以上に荒れた状態になっていた。住民が避難に及んだ最短は37時間後、別の地域では3日後、7日後、1か月後、それ以降・・・など、さまざまだ。13万5000人が暮らしていた原発から30キロ圏内は危険区域に指定された。その一軒の民家で日めくりカレンダーを偶然に目した。壁に貼られた「1986年5月4日」。こんなに長い間、高放射能のなかで暮らしていたのかと驚愕しながらレンズを向けた。この家族はどこかで無事に暮らしているのだろうかと、その時の写真を見入りながら今も思いを馳せる。
そのころ、30キロ圏内に戻ってきたお年寄りたちがすでに1300人ほど住んでいた。65歳のある女性は「避難はしたけれど、ふるさとで死にたいから。でも電気も店も交通機関もない。まるで収容所みたい」と嘆いた。彼らは汚染された土地で栽培したものを食べるしかない。そこに、孫たちが遊びにやって来る。「短期間だけだから大丈夫」とお祖母さんは小学生の孫息子を甘えさせながら言っていた。彼は元気に成長しているだろうか。
その後も何度かチェルノブイリ被災地を訪ねて歩いた。度ごと気にかかったのは、子どもたちの健康状態だ。甲状腺癌は最も顕著に原発事故の後に急増しているけれど、それ以外の癌、貧血や視力の低下も見過ごせないし、下痢、発熱、頭痛、そして心臓疾患などで入退院を繰り返す子どもたちが「増えた」と医師は私に訴えるように話した。特に避難地域では爆発当日、屋外にいたか屋内かで症状に格差が現れたという。低線量汚染地域でも、教員たちが口々に話したのは「免疫力の低下」による影響だった。「風邪をひいてもかつては3,4日で治ったものが1か月もかかる」。またウクライナのある児童施設を訪ねると、生まれながらの障害も以前に比べて激増したと保育士は顔を曇らせていた。
子どもたちの健康障害は社会や大人のさまざまな身勝手から来ていることは言うまでもない。未来を担う子どもの健康といのちを筆頭にした政策や環境を作らなければ、その国の将来は不安に見舞われる。弱い立場にある子どもを護れば、おのずと大人も護られることになる。チェルノブイリ原発事故は事故の情報公開や責任のあり方、放射能汚染の対策、人びとへの対処の仕方、健康など多義にわたって教訓を残した。それを活かしていくことこそが子どもを健康な成人にするために欠かせないはずだ。
問題はチェルノブイリにとどまるものではなく、とりわけ「フクシマ」と直面している日本にとって学ぶことが多い。