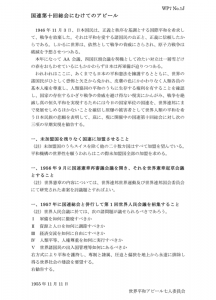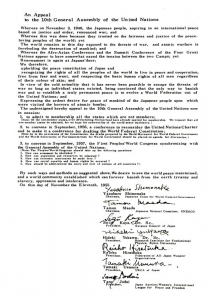「大学・研究機関等の軍事化の危険性を、国民、科学者・技術者、大学研究機関等、ならびに日本学術会議に訴える」と題するアピールを発表しました。
作成者別アーカイブ: wp7
2017 123J 大学・研究機関等の軍事化の危険性を、国民、科学者・技術者、大学研究機関等、ならびに日本学術会議に訴える
2017年2月24日
世界平和アピール七人委員会
武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晋一郎 髙村薫
内閣府が“専門家”による国家安全保障と科学技術の検討会を発足させることにしたと、報じられている。国の科学技術政策を決めて予算に反映させる総合科学技術・イノベーション会議(議長:安倍首相)における軍民両用技術の研究推進政策の具体化に向けて、早急に作業するというのである。
これは2012年の第二次安倍内閣の発足以来、特定秘密保護法成立と防衛大綱・中期防衛力整備計画の閣議決定、「防衛装備移転3原則」の閣議決定による武器輸出の解禁、「防衛生産・技術基盤戦略」の公表、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法の成立、共謀罪の企みなど、平和主義・民主主義・基本的人権尊重など日本国憲法に則った精神を踏みにじり、国の将来を危機に陥れかねない法律制定や閣議決定をかさね、軍国主義への道をひた走っている動きの一環である。
この動きの中に、2016年1月に閣議決定された第5期科学技術基本計画に記載された「国家安全保障上の諸課題への対応」があり、学術を軍事研究に積極的に動員する動きが公然と進められている。
安全保障関連法の成立によって発足した防衛省の防衛装備庁は、重要課題の第1に「諸外国との防衛装備・技術協力の強化」、第2に「厳しさを増す安全保障環境を踏まえた技術的優位の確保」を挙げている。そして「装備品の構想から研究・開発、量産取得、運用・維持整備、廃棄といったライフサイクルの各段階を通じた、一元的かつ一貫した管理が必要」なので、プロジェクト管理部に、文官、自衛官を配置し、プロジェクトマネージャーの下、性能やコスト、期間といった要素を把握して、効果的かつ効率的に行っていくための方針や、計画を作成し、必要な調整を行うと述べている。
この方式は、米国国防総省の国防高等研究開発局(DARPA)方式の踏襲であって、自由な研究の成果が民生にも軍事にも利用できるというデュアルユースではなく、目標を決め、そのために事前に何をしなければならないかを選定し、これを繰り返して最初に手をつけなければならない課題を選び出す。最初の課題だけを見れば、民生にも軍事にも応用できるテーマに見えるが、上で見たように“防衛装備”という「武器あるいは武器に関する技術」の開発の第1段階であって、軍事に支障のない範囲だけが民生用に提供されることになる。
このような情勢の下で、2004年に開始された防衛省と大学・研究機関を含む民間との共同研究協定が2014年度から急増し、2015年度からは「安全保障技術研究推進制度」による大学・研究機関等への委託研究費が、年3億円、6億円、110億円と拡大されている。
さらに米国の軍機関から日本の大学・研究機関等に長年にわたり研究資金が提供されてきたことも、報道機関の調査によって2017年2月に明らかにされた。
私たち世界平和アピール七人委員会は、国民一人一人が判断し声をあげるよう訴える:日本の科学・技術の成果が、武器あるいはその部品として諸外国に輸出され、米国やイスラエルなど海外との武器の共同開発によって実際に戦闘に使われ、殺戮に手を貸すことになってよいのか。諸外国より優れた“防衛装備”の開発を公然と唱えることによって世界の軍拡を促しているのではないか。「敵基地攻撃の装備を持つ方がよいという議論がある」と政権党の副総裁がいう。これが戦争を放棄した憲法の下での日本の姿であってよいのか。
科学者・技術者に訴える:全体像が隠されて、最初の基礎や萌芽的な段階だけを見せられて、平和にも役立つといった素朴な感覚で防衛省の予算を受け、海外の軍資金を受けてよいのか。私たちは、制約や秘密を伴う研究はいかなるものであっても受けるべきでないと考える。
大学・研究機関等に訴える:軍機関からの資金導入の場合の注意などといった生ぬるい感覚でよいのか。私たちは、構成員の間で広く議論を重ね、毅然たる規定を作り、内外の軍機関からの資金は受け入れず、大学・研究機関等の内部では企業との間でも、制約や秘密を伴う研究は避けることを求める。そのためにも一定規模以上のすべての外部資金の実態が公開されることを求める。
学術団体、学協会に訴える:軍資金であっても直接の兵器開発研究でなければ問題ないといった感覚は支持できない。国内外を問わず、軍隊、自衛隊からの援助を受けず、その他一切の協力関係を持たないでいただきたい。
日本学術会議とその会員に訴える:2016年6月以来、毎月公開で議論を重ねてきた「安全保障と学術に関する検討委員会」は2017年2月の委員会で「中間とりまとめ」を確認した。多様な意見が存在する組織の共通の見解として、理想的でないにしても、委員会の努力を評価したい。ただ3月の最終回委員会でさらに詰めるべき点が残されているし、幹事会、4月総会でどのように扱われるか、状況は予断を許さない。
政府が判断を誤り、情報操作によって国民に真実を知らせない中で、戦争に全面的に協力した科学者の反省から、第2次世界大戦終結から3年半後の日本学術会議第1回総会で行った「日本学術会議の発足にあたって科学者としての決意表明」、翌1950年4月の声明「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明」、1967年5月の会長見解と10月の「軍事目的の科学研究を行わない声明」を名目だけでなく継承し、総会が国民の信頼を損なうことのない判断をされることを期待する。さらに、風化・空洞化を防ぐために繰り返し広く科学者の中での討議を重ねていくことを期待する。
PDFアピール文→ ![]() 123j.pdf
123j.pdf
今月のことばにNo.31「核兵器廃絶への軌跡とこれから」を掲載
2016年講演会
「沖縄は日本なのか」 七人委、法政大・沖縄文化研究所と2016年講演会
世界平和アピール七人委員会は、11月19日(土)東京・市ヶ谷の法政大学で、「2016年講演会」を開いた。テーマは「沖縄は日本なのか-〈平和〉を軸として考える-」。同大学の沖縄文化研究所との共催で、300人を超す聴衆が集まった。
講演会では、大石芳野委員が自身の撮影した写真をもとに話したほか、小沼通二委員・事務局長、武者小路公秀委員、高村薫委員、それに法政大学の杉田敦教授が講演、後半はシンポジウムで議論を深めた。
小沼委員・事務局長は、「世界平和アピール七人委員会は1955年11月11日発足した。ビキニの水爆実験の翌年であり、国連10周年、ラッセル・アインシュタイン宣言の年でもあった」と話し、発足以来の活動を紹介した。
最初の講演は大石委員。東村高江地区のヘリパッド建設問題に触れた後、かつての戦争の遺物や証人たちの写真をもとに、「沖縄戦の傷は今も残っている。戦争は終わっていない」と訴えた。
▼求められる「植民地・沖縄」「見捨てた沖縄」への謝罪
続いて武者小路委員は、「沖縄をイメージすることの難しさ」と題して、「沖縄は歴史的にも、国際的な位置としても、また文化の面からも、ヤマトとは違うカオがある」として、「琉球王国時代は中国からは礼楽の属国として、欧米からは琉米条約、琉仏条約に見るように、対等な国として、また日本からは鎖国日本と欧米の緩衝国としてのカオだったし、今の沖縄でいえば、日本から見れば占領地から日本に復帰した地方自治体、国連から見れば先住民族としての自治権を認められるべき被差別主体であり、米国からは『米日衛星協力体制』の中で、日本による実質支配が優先する、琉米条約の対象国だ」と説明。「いまヤマトから見れば、日中和解を作ることができる『守礼の国』だし、生命多様性を保証する先住民族島嶼国だ。しかし、ヤマトは沖縄を植民地とし、沖縄とヤマトとの間には歴史の事実を認めた和解がない。ヤマトは沖縄を植民地とした反省から始めなければならない」述べた。 そして最後に、「この日琉の和解はきっと世界の南北対立の和解に押し広げることの大前提になる。植民地侵略の被害を受けた沖縄と、植民地侵略を懺悔するヤマトとが和解し一致団結することで、日本国は初めて『日米永世中立』の中で国際社会の和解を導くクニになれる。日本の国際的な南北和解を進めるうえで、ヤマトに併合された琉球王国を継承する沖縄が、日本国家の反植民地主義を代表してくれることを、ヤマトが沖縄に依頼する姿勢をとるべきだ」と強調した。
「異化する沖縄」と題して話したのは高村委員。「沖縄は日本なのか、という問い自体おかしい。しかし、改めてそう問われると、本土の人間は困ってしまう」と切り出した。
「行政の行動に反対する運動はほかにもあるだろうが、高江の闘争はほかでは見られない。その背景には『負の住民感情』がある。米軍による犯罪も含め、この『負の住民感情』の対象は実は日本だ。もともと沖縄の人たちは争いを好まない人たちだが、沖縄を見捨てて沖縄戦をたたかい、基地の集中を丸呑みした日本に対し、憎しみが残った。満蒙開拓団の人たちは日本軍に逃げられて見捨てられたが、憎い日本とは思わない。しかし、沖縄は日本になろうとして裏切られた。日本でいるしかないから、異化し続ける。沖縄の人たちは自らを異化することで、本土に、永田町に、理解を求めている」と強調。「本土の人間として、その憎い日本を思い起こした上で、沖縄のことを知る。沖縄は日本なのか、と聞かれて日本だと答えられるようにしなければいけないと思う」と結んだ。
▼メディアが書かないことも問題
杉田教授は、「沖縄のことは関係がない、と思うこと自体が一番問題なのだと思う」と前置きして、①沖縄は日本の捨て石として地上戦が戦われた ②日本は沖縄を差し出すことで、独立を達成した ③返還時にも欺瞞があった。「本土並み」はウソだったし、「核抜き」も疑わしい ④返還後、本土の基地が沖縄に移転した ⑤基地負担は民意を無視して行われており、減らすどころか新基地を造ろうとしている ⑥本土のメディアは取り上げることが少なく関心が薄くされている―などと問題点を指摘した。
そして、関心が薄い理由について、①本土には迷惑施設を他の地域に押しつけるのと同じ「利己主義」がある ②地方蔑視がある。基地経済の意味はもう小さいのに、基地がなければ成り立たないという勝手なイメージで扱われている ③これまでの歴史も差別の構造も考えない差別意識が根強い―と述べ、「沖縄は地政学上の位置から基地は仕方がない。騒ぐのは沖縄のエゴだ、という人がいるが、これはおかしい」と指摘した。
この後、会場の質問に答えながら、全員がシンポジウムで発言。問題の深刻さをかみしめた集会だった。








「言うべきときに 言うべきことを ―私たちのアピール」を発刊
 13年分のアピールを収録
13年分のアピールを収録
世界平和アピール七人委員会は、このほど、2004年からこの11月まで、世界に向けて発信してきたアピールをまとめて、「言うべきときに 言うべきことを―私たちのアピール」を発刊しました。
七人委員会は1955年、下中弥三郎、平塚らいてう、湯川秀樹らによって発足して以来、メンバーは入れ替わりましたが、平和と人権、民主主義と、日本国憲法擁護、核兵器廃絶などについて、おりに触れてはアピールを発表してきました。アピールは、この11月2日に発表した「南スーダン派遣自衛隊は停戦成立まで活動の停止を」まで、合計122本に及びました。
今回まとまったアピール集は、メンバーの補充が間に合わなくて活動が休止していたのち、新しく5人が加わって活動を再開した2004年からのアピール40本をまとめたものです。アピールは、秘密保護法、安保関連法、沖縄など国内の問題から、原発、核兵器廃絶、環境、「イスラム国」問題まで、日本と世界の情勢を見詰め、日本人としての自覚的立場から、どう考えるべきか、どうあるべきかを訴え続けています。何を言うかだけでなくどうしてこのような発言をするのかまで書きましたからいま、お読みくださっても十分ご参考になると思います。日本が直面している問題や世界情勢についても、基本的な立場を確認し、あるべき姿を考える素材となるものだと思います。ぜひ、手元に置いて、読み返していただきたいと考えます。頒価は1冊500円、送料200円です。
申し込みは、このホームページの 『連絡先』 から申し込んでいただくか、直接、事務局の日向和子(メール
また、委員、他の事務局員にご連絡くださっても結構です。。
アピール「南スーダン派遣自衛隊は停戦成立まで活動の停止を」を発表
「南スーダン派遣自衛隊は停戦成立まで活動の停止を」と題するアピールを発表しました。
2016 122J 南スーダン派遣自衛隊は停戦成立まで活動の停止を
2016年11月2日
世界平和アピール七人委員会
武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晉一郎 髙村薫
私たちは、南スーダンへの自衛隊派遣を直ちに中止し、派遣部隊を速やかに国外に退去させるべきだと考える。
政府は2016年10月25日に、10月までとされていた南スーダンへの自衛隊派遣期間を2018年3月まで延長した。これと同時に、首都ジュバを含めて各地で武力衝突や市民の殺傷が頻発している中で、撤退しない理由として、「派遣継続に関する基本的な考え方」を内閣官房、内閣府、外務省、防衛省の連名で発表した。
この発表では、「駆けつけ警護」任務を追加しようとしていたのだが、対応できる情勢ではないため、11月に予定されている第11次要員の出発直前まで決定を延期せざるを得なかったのだと思われる。
自衛隊員は日本国憲法第99条によって国家公務員として憲法擁護義務を負っている。日本国憲法は、戦力を保持せず、国の交戦権を認めていない。自衛隊は他国の軍隊に劣らない武装をしていても戦力を行使できず、軍隊ではなく、専守防衛に徹してきたのもそのためである。
この日本国憲法の基本原則のもとで国連の平和維持活動(PKO)に協力するために作られたのがPKO参加5原則だった。
南スーダンに2011年以来自衛隊の司令部要員を派遣し、2012年から施設部隊を派遣している日本政府は、現在でもこのPKO参加5原則の下で派遣していると言明している。実際、派遣されてきた陸上自衛隊は施設建設維持が任務であって、荒廃した国土の道路や橋梁の復興支援の任に当たってきた。
ところが、国連安全保障理事会は、今年7月南スーダンの首都ジュバで起きたキール大統領派とマシャール前第1副大統領派の間で起きた激しい戦闘を見て、より積極的な武力行使の権限を持つ地域防護部隊4000人の派遣を8月に決定した。この決定は、PKO 5原則の第1項にある「紛争当事者間で停戦合意が成立していること」が満たされていないことを明白に示している。事実、マシャール氏は10月26日「首都攻撃も辞さない」と宣言しており、停戦合意が崩壊していることは明らかである。支援活動を続けてきた日本のJICA(国際協力機構)が、活動を中断し国外退去を余儀なくされたことも停戦が行われていないためである。
日本政府は、いわゆる「駆けつけ警護」の役割も持たせる普通科部隊を、短期間の訓練によって派遣する計画だが、それは実施すべき選択ではない。PKO参加5原則によって、武器使用は必要最小限度という条件があるため他国の軍隊と同じ活動はできないし、相手は日本国憲法にしばられることがないのだから、どう考えてもこのままの継続はありえない状況だといえる。
内閣府が3年に一度ずつ行ってきた世論調査の最近の結果を見れば、自衛隊の災害救助活動は評価されているけれど、PKO活動の拡大は支持されていない。
日本政府は、派遣延長ができる状況ではないので、「日本の自衛隊は軍隊でないため、地域防護部隊への参加はできない。PKO参加5原則が安定して満たされる段階になれば施設部隊を現地に戻し積極的に復興に貢献させる」と宣言して、活動を直ちに停止させ、いったん国外に撤収させる方法を直ちに検討しなければならない。
PDFアピール文→ ![]() 122j.pdf
122j.pdf