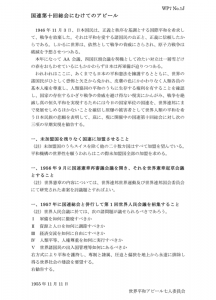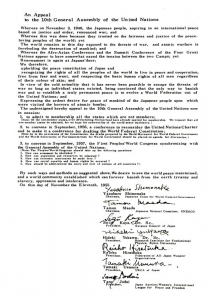ハンマーを持つ人
池辺晋一郎
先日、アメリカのジャーナリストにして映画監督ジャン・ユンカーマン氏の発言に、新聞紙上で接した。
1952年ミルウォーキー生まれ。生後まもなく、1年間くらいらしいが神奈川県葉山に住み、のちに慶応義塾志木高校で学んだという人である。
その後スタンフォード大学、ウィスコンシン大学に学んだ。ベトナム戦争時代に学生生活を送り、反戦や徴兵制反対運動に身を投じた。
長じて、まず88年に映画「劫火」(ごうか)を撮る。
90年には「老人と海」、92年「夢窓──庭との語らい」でエミー賞を受ける。
そして「映画・日本国憲法」を撮ったのは2005年。
そのユンカーマン氏の発言──集団的自衛権は、すなわち交戦権である。
平和憲法を持つ日本は世界の尊敬を集める立場だったのに、これを捨ててアメリカに従うとは…。
安倍首相は日本を、戦争ができる「普通」の国にしようとしている。
朝鮮半島、ベトナム、アフガニスタン、イラク…どこも戦争の後遺症に苦しんでいる。武力では何も解決できないことは、歴史が証明している。
そして、アメリカの格言を紹介している──ハンマーを持つ人にはすべてが釘に見える。
このことを初めて紹介したときは、政府の閣議決定が間近に迫っているときだった。
しかし政府は、反対の声の高まりにもかかわらず、あっさりと、集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈変更を決めてしまった。
自民党内にも、これに反対するハト派がいたはずなのに、ここに至ってこのハトは全く啼かない。
さらに呆れるのは公明党だ。「平和の党」を標榜していたのに、その理念を捨てて、連立政権の椅子に固執したわけ。
公明党は安倍政権のブレーキ役だと見做していたが、何ともだらしない、見苦しい変節だ。
「必要最小限」「歯止めがある」「容認は限定的」などということばは、すべて苦し紛れ。弁解にしか聞こえない。
いったい、現行憲法をどう読めば、そんな解釈が可能になるのか…。中学や高校の国語の文章解釈試験で答えたら、バツがつきます。
毅然・明解な憲法条文に比して、前記の弁解は曖昧。不明確。
「必要最小限」か「やや小」なのか、誰が決める?
為政者が「歯止め」と言えばそうなるのか?
「限定」の範囲を越えるか越えないかを判断するのは、誰?
厳格に設けられている堰を、いっぺん切ったらどういうことになるか。流れ出す水を、都合よく再び堰き止めるなんてこと、できる?
今、日本の政府は、厳格な堰を切ろうとしているのだ。
僕は、憲法前文の中の「われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」という一節に、いつも感動する。
「名誉ある地位」という言いかたのすばらしさ!
その名誉を捨てようというのだ。ユンカーマン監督の言うとおりである。
ハンマーを持つ人になってしまう日本…情けない限り。
(「うたごえ新聞」2385号、2014年7月14日付掲載、「空を見てますか」925回を修正、転載しました。ユンカーマン氏の発言は、朝日新聞2014年6月24日に掲載されています。)